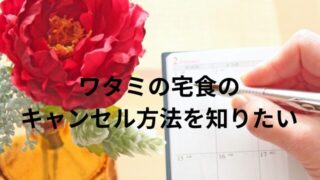【大豆製品は豆腐よりおからがいいかも!?】女性の美と健康維持に欠かせない4つのスゴイ栄養が入っている

豆腐を作るために大豆を絞った汁が豆乳で、
絞りかすが「おから」です。
おからって栄養があまりないのでは?
と思われがちですが実は大変栄養豊富で
シニア女性は特に積極的に食べたい食材の一つです。
おからはある意味、豆腐よりもおすすめしたい!
私の推しの「大豆製品」その理由とおからのすごい栄養
についてご紹介します。
目次
おからについてちょっと詳しく
【おから】はスーパーの豆腐や油揚げ売り場の隅っこに
ひっそりたたずんでいて?地味な印象です。
値段も安く300g入って60~70円程ほどの【おから】は
「生おから」です。
豆乳を絞った後なのでしっとりしています。
 生おから。
生おから。
生おから以外にも長期保存が可能な、
●生おからを乾燥させた「乾燥おから」
●乾燥おからを粉末にした「おからパウダー」
があります。
 乾燥おから。
乾燥おから。
乾燥おからはところどころ粒が混ざっているタイプが多く、
そのまままたは水に戻して料理に使うことができます。
 おからパウダー。
おからパウダー。
おからパウダーはその名の通り粉末状になっているので、
小麦粉や米粉などのように料理やお菓子作りに使えて便利。
もちろん長期保存もできます。
おからのメリット
おからの全体的なメリットは、以下の通りです。
値段が安い。
生おからは他の大豆製品に比べて格段に安く手に入ります。
節約食材としてはぴったり。
入手しやすい。
スーパーなどで日常的に手に入る身近な食材です。
栄養豊富。
食物繊維や大豆イソフラボンなどが女性が摂りたい栄養が豊富に含まれています。
低カロリーで高たんぱく。
おから100g当たり約80kcalと低カロリーなのに、たんぱく質は6g
と高たんぱくなのが特長。
満腹感を得やすい。
おからを煮た料理「卯の花」を作るとわかるのですが、
おからは水分を吸収しやすい食材です。
よって少量でもお腹に入ると水分を含むことで満腹感を得やすく
なります。
カサ増ししやすい。
生おからは特にカサがあるので、野菜やこんにゃくなど他の低カロ食材と
組み合わせてカサ増ししやすい。
おからのデメリット
おからにはメリットがある反面、デメリットもあります。
日持ちがしない。
生おからはしっとりとしていて水分が多いため傷みやすく、
賞味期限が2日ほどと短くなっています。
ぼそぼそとした食感。
おからの持つぼそぼそとした食感が苦手という方も・・・
食べ過ぎで便秘に?
おからの食物繊維は「不溶性食物繊維」なので、
食べ過ぎると便が固くなる恐れがあります。
大豆アレルギーの方は注意。
味付けが難しい?
おからは水分を吸収しやすいため、おからを使った煮物=
卯の花を作るときは味加減がわかりづらく、つい味付けが
濃くなってしまうことも。
おからの持つ栄養がすごかった
メリットデメリット両方あるおからですが、
栄養豊富である点においては、積極的に買いですよね。
具体的にはどんな栄養が含まれているのでしょうか?
少し前述しましたがおからには、
●食物繊維
●大豆イソフラボン
など特に女性が摂りたい栄養が豊富です。
また大豆は「畑の肉」とよく呼ばれますが、植物性のたんぱく質が
豊富に含まれているほか、「大豆のこんな小さい1粒に!」
と驚くほど実にさまざまな栄養がぎっしり詰まっています。
食物繊維
おからには、
●水溶性食物繊維
●不溶性食物繊維
の2種類がバランスよく含まれています。
腸内で便のカサを増やしたり便通をスムーズにして、
大腸がんの予防に役立つほか、
コレステロールの吸収や血糖値上昇を抑える働きも期待できます。
なお大豆に含まれる炭水化物には、腸内の善玉菌を増やす働きのある
オリゴ糖が豊富です。
腸内環境をよくするのにもおからの食物繊維が役立ちそうです。
大豆イソフラボン
大豆イソフラボンは大豆に含まれるポリフェノールの一種で、
体内に入ると女性ホルモン「エストロゲン」と似た働きをします。
ホルモンバランスの乱れから来る更年期の様々な症状を和らげる
のに役立つほか、骨粗しょう症やがんの予防などにもおすすめです。
大豆サポニン
大豆サポニンは大豆が持つ苦みや泡立ち成分のもとで、
大豆の胚芽に多く含まれる成分です。
大豆サポニンは抗酸化作用に優れ、体内では過酸化脂質=腐った脂肪!
の生成を抑えるほか、活性酸素を除去して細胞の老化を防ぎます。
また脂肪の吸収を抑え燃焼しやすくする効果や、
免疫細胞を活性化させる働きもあり、免疫力アップの効果も期待できます。
カルシウム
おからにはカルシウムも豊富です。
生おから100gあたり約81mg、
乾燥おから100gあたり約310mgのカルシウムが含まれています。
カルシウムの1日の摂取目安量は、
成人男性が750mg、成人女性が650mgとされています。
(日本人の食事摂取基準2020年度版)
よっておからが効率よいカルシウムの摂取源であることがわかるでしょう。
カルシウムは体内で吸収されにくい成分ですので、意識的に摂るように
する必要があるのですが、牛乳などの乳製品はカロリーも気になることから、
おからをカルシウムの摂取源の一つに加えるといいでしょう。
鉄分
おからには意外にも「鉄分」が豊富です。
おからに含まれる鉄分は植物性で「非ヘム鉄」です。
乾燥おから100gあたり約4.9mg、
生おからでは100gあたり約1.3mgの鉄分が含まれています。
鉄分不足というと若い女性や妊産婦を思い浮かべますが、
閉経後の女性も鉄分不足に陥ることがあります。
これは加齢による栄養吸収率の低下やコーヒーや緑茶など
カフェインを含む飲み物の飲みすぎなどが挙げられます。
もし普段から疲れやすかったりだるさを感じることが多かったら、
鉄分不足かもしれませんので、おからを鉄分補給減として
利用してみてください。
豆腐との栄養を比較
口当たりがよく食欲がない時でもつるっと食べられる「豆腐」ですが、
栄養面では実はおからにはかなわない部分があります。
 豆腐とおからと大豆。
豆腐とおからと大豆。
豆腐は90%が水分であることを考えると当然なのですが、
おからは豆腐に比べてたんぱく質やカリウムが豊富で、
特に食物繊維は豆腐の約10倍以上も含まれています。
しかし豆腐もおからに負けず低カロリー高たんぱくですので、
その点は大いにメリットがあります。
よって食べる目的に応じて豆腐とおからどちらを選ぶか違ってくるでしょう。
消化のいいものを食べたい、柔らかいものを食べたい。
豆腐
食物繊維をしっかり摂りたい、少量でも満腹感を得たい。
おから
という感じでしょうか?
おからを食事に取り入れる方法
おから料理と言えば「卯の花」ですが、
自分で作るのが面倒なら市販のお惣菜を使うのもGOOD。
生おからを料理に使う場合はそのまま使うと粒やダマが残りやすいので、
フライパンなどで「乾煎り(からいり)」してから使うことをおすすめします。
乾煎りしたおからは、
ひき肉と混ぜて「おからハンバーグ」
サラダのトッピングに
汁物の具に
小麦粉や米粉などと混ぜてお菓子作りに
などアイデア次第でいろいろな使い方ができます。
乾燥おからでもっと気軽に
ただ前述したように生おからは傷みやすいため、
気軽に食べるなら日持ちしていつでも使える乾燥おからや
おからパウダーを利用する方がいいかもしれません。
例えばスープやヨーグルトにおからパウダーをササっと1さじ
入れたり、
焼きっぱなしケーキの生地の一部に乾燥おからを混ぜてみたり、
お好み焼きの生地におからパウダーを混ぜてみたり、
と思い立ったらすぐに混ぜることができるので、常備しておくと
とても便利です。
 おからと豆乳のケーキ。
おからと豆乳のケーキ。
料理への使い方はおからパウダーや乾燥おからのパッケージにも
記載されているので、参考になさってくださいね。
まとめ
おからは食品廃棄物の中でも最も量が多く、
食用に利用されているのは全体の1%くらいと非常に少ないのが現状です。
余ったおからは飼料や肥料、それでも残ったら廃棄処分されています。
やはり傷みやすいことが廃棄の最大の理由です。
でも・・・
こんなに栄養が豊富なのにおからを捨てているなんて
もったいないと思いませんか??
おからの廃棄が多いことを知ってからは、
家庭で使う量はたかが知れているかもしれませんが、
乾燥おからでもいいので少しでも利用して
消費量アップにつなげたいと思うようになりました。
ぽちっとワンクリック、
応援よろしくお願いします!
>> ブログランキング